インド法の基礎知識
【Q1】インドの法体系について教えてください。
インドは、イギリスの大きな影響を受け、「判例」を重視するコモンローをベースにしつつも、日本の法体系と同じく多くの「制定法」が取り入れられています。
インドは民主国家であり、制定法は、憲法に基づき議会と州議会によって制定されるため、共産主義国や独裁主義国家と異なり、法的安定性が確保されることが魅力です。
司法機関については、最高裁判所を頂点とし、各州に高等裁判所、その下に地方裁判所、家庭裁判所、日本でいう簡易裁判所などのいくつかの種類の下級裁判所が存在します。
【Q2】ビジネスに関連する主要な法律について教えてください。
ビジネス分野については、主に成文法に基づいて運用されており、主要な法律には、会社法、競争法(日本の独占禁止法に相当)、物品・サービス税(GST)に関する法律、知的財産法などがあり、日本と同水準の法律が整備されています。
それぞれの法律とこれに関連する規則や規制等は、所管するインド政府機関等のウェブサイトで最新の情報が確認できます。とはいえ、その複雑さから、実際の適用や法適合性の検討のためには、多くの場合は、法的専門家への相談が必要になります。
【Q3】インドの連邦法と州法の関係について教えてください。
インドは28の州と8つの連邦直轄領から成る連邦共和国です。
インド全体に適用される法律(連邦法)と州ごとに適用される法律(州法)があります。
連邦(中央)政府と州政府の立法権の範囲はインド憲法に定められており、次の3つに分類されます。
1.ユニオン・リスト:連邦にだけ立法権がある
2.ステイト・リスト:州にだけ立法権がある
3.コンカレント・リスト:連邦にも州にも立法権がある
コンカレント・リストに定められる事項について、連邦法と州法で相反する立法がされた場合、州法は効力を認められず、連邦法が適用されます。例外的に、連邦が承認することで、連邦法に矛盾する州法を有効とすることができます。
詳しくは、インド憲法の第7附表(310-324頁)で確認できます。これはインド法務省のウェブサイト(https://legislative.gov.in/constitution-of-india/)で入手できます。
【Q4】インドの法務関連の文書は英語で利用できますか?
インドでは英語が公用語の一つとして広く使用されており、法律文書やビジネス関連の情報も英語で提供され、各法律とこれに関連する規則や規制等は、所管するインド政府機関のウェブサイトで英語で提供されています。
また、インドの裁判手続は主に英語で執り行われ、判決書も英語で作成されます。ただし、一部の州では裁判において英語に加えてヒンディー語の使用が許可されており、一部の下級裁判所ではヒンディー語で裁判が行われますので、注意が必要です。
インド進出の基礎知識
【Q1】インドへの外国人による投資に関する規制について教えてください。
インドでは、主に外国為替管理法(FEMA)と外国直接投資(FDI)政策の2つにより、外国投資(一定の国境を越えた資金や資産の移動)が規制されています。外貨の取引や国際的な送金、投資、貸付などを対象としており、インド経済の安定や安全を確保するために導入されています。
インド非居住者による会社設立や既存の会社の株式取得や土地の取得、国境を超える貸付などが、規制の対象となります。
例えば、インド非居住者による会社設立や株式取得については、業種ごとに規制の内容が異なり、参入が禁止されるもの(カジノ事業、投資目的の不動産事業など)、政府の明確な承認が必要なもの(政府ルート)と、政府の承認を要しないもの(自動ルート)があります。
業種ごとにインド非居住者による出資比率の上限が定められていますが、近年の規制緩和により、多くの業種において自動ルートによる100%出資が認められています。
自動ルートでの投資の場合でも、インド準備銀行への事後報告が必要となり、取得する株式の価格については「価格ガイドライン」よる価格規制があります。
FDI規制は、世界経済の動向に合わせて頻繁に更新されるため、DPIITのウェブサイト(https://dpiit.gov.in/foreign-direct-investment/foreign-direct-investment-policy)を定期的に確認する必要があります。
【Q2】FDI規制のうち、政府ルートの対象となる産業分野について教えてください。
例えば、次のような産業があります。
- 防衛産業
政府ルートで最大100%の外国直接投資(FDI)が許可されますが、74%を超える出資には政府の承認が必要です。 - 小売業
最大51%のFDIが許可されますが、特定の条件を満たす必要があります。 - ブラウンフィールドによる製薬業
既存施設を利用した製薬業については、最大74%まで自動ルートで許可され、それを超える場合は政府の承認が必要です。 - 印刷メディア
最大26%のFDIが政府ルートで許可されます。 - 宇宙産業
最大74%まで自動ルートで許可され、それを超える場合は政府の承認が必要です。
規制の状況はグローバル経済の動向に合わせて頻繁に更新されるため、DPIITのウェブサイト(https://dpiit.gov.in/foreign-direct-investment/foreign-direct-investment-policy)を定期的に確認する必要があります。
【Q3】FDI規制のうち、自動ルートで100%外国投資が認められる産業分野について教えてください。
例えば、次のような産業があります。
農業、畜産、自動車部品、自動車、バイオテクノロジー、建設開発、IT、食品加工、製造業全般、医療、再生可能エネルギー
規制の状況はグローバル経済の動向に合わせて頻繁に更新されるため、DPIITのウェブサイト(https://dpiit.gov.in/foreign-direct-investment/foreign-direct-investment-policy)を定期的に確認する必要があります。
【Q4】インドに進出するには、どのような方法がありますか?
インドに進出する方法として、①駐在事務所、②支店、③プロジェクト・オフィス、④法人の設立、⑤有限責任組合(LLP)があります。④法人設立には、(ア)プライベート・リミテッド・カンパニー(日本の株式会社に相当)、(イ)パブリック・リミテッド・カンパニー(ウ)保証有限会社(日本の合資会社に類似)、(エ)無限責任会社(日本の合名会社に類似)、(オ)一人会社があります。なお、(オ)一人会社は外国人が設立することは認められていません。
①駐在事務所は、事業開始前の市場調査やネットワーキング、親会社の宣伝を目的とする場合に最適ですが、営業活動を行うことはできません。
②支店は、輸出入、専門サービス(法律、会計、医療、IT、人材派遣など)、研究活動などの一定の営業活動のみが許可され、インドでの製造・加工はできません。
③プロジェクト・オフィスは、特定のプロジェクトが終了するまで、当該プロジェクトに関する活動のみが許されており、プロジェクト完了後は撤退(閉鎖)することになります。
④法人設立は、長期的な事業運営に最適です。詳細は次のQAを参照ください。
他にも、インドに進出する方法として、インド現地のパートナーと⑤合弁契約を締結して会社を設立する方法、⑥販売代理店契約を締結する方法があります。
【Q5】インド進出でよく利用される法人形態について説明してください。
1. プライベート・リミテッド・カンパニー
インドで長期的かつ大規模なビジネス展開を目指す場合に、最適です。
この運営は柔軟性が高く、日本の株式会社に類似しているため、法規制について理解しやすいというメリットがあります。最低資本金はなく、外国人のみでの設立が可能です。ただし、取締役のうち少なくとも1名は当該会計年度に合計182日以上インドに滞在する必要があります。
また、2名以上の株主が必要になります。この要件を満たすために、いわゆる名義株主にわずかな株式を保有させることが実務上行われます。
2. パブリック・リミテッド・カンパニー
プライベート・リミテッド・カンパニーに似ていますが、株式市場への上場が可能で、より多くのコンプライアンス要件が課されます。
3. 有限責任組合(LLP)
比較的小規模なビジネスで利用されます。2名以上の組合員が必要になり、組合員が全員法人でない場合は、組合員の一人はインド居住者である必要があります。規制緩和により使い勝手がよくなっており、利用が増えています。
【Q6】インドでプライベート・リミテッド・カンパニーを設立するために基本的な手順について教えてください。
インドでプライベート・リミテッド・カンパニーを設立するには、会社設立の申請を行う必要があります。
その申請の準備として①電子署名認証(DSC)の取得、②取締役になろうとする者の識別番号(DIN)の取得、③会社名の承認申請を行う必要があります。
①~③の手続が完了した後、会社設立の申請書と添付書類をオンラインで提出して申請します。日本と同じく定款を作成し、承認された会社名等を付して提出します。申請書は、インド企業省のウェブサイトの書式を利用することができます。
添付資料は、公証役場での公証等を受ける必要があります。申請書類に不備がなければ、1~2週間で手続が完了します。
事業を開始するには、引受株式の全額の払い込みがされたことを取締役等が証明する旨の書面を会社登記局に提出する必要があります。
また、株式発行について、発行から30日以内にインド準備銀行に報告する必要があります。
【Q7】電子署名認証(DSC)とは何ですか?
電子署名認証(DSC)とは、電子署名の登録といい、日本の印鑑登録制度の電子版といえます。
会社設立、税務申告、その他の行政手続をオンラインで行う場合、必ずDSCが必要になります。
申請に必要な添付資料は公証等を得たものである必要があり、原文と翻訳の正確性について誓約書が必要になります。通常、専門業者に委託して行い、不備がなければ申請から1週間程度で手続が完了します。
【Q8】取締役識別番号(DIN)とは何ですか?
取締役識別番号とは、各取締役個人に対して付与される番号です。DINは一度登録すると生涯有効です。したがって、以後、取締役に任命される際に再度手続を行う必要はありません。
DINの申請は、インド企業省のウェブサイト上の書式を利用して、オンラインで行うことができます。身元確認書類および住所証明書の提出が必要です。外国人の場合、これらの書類にアポスティーユまたは公証が必要です。
申請内容に不備がなければ、数日から1週間程度で手続が完了します。
【Q9】商号承認申請について教えてください。
会社設立申請の前に、設立予定の会社名について、会社省(MCA)ウェブサイト上のRUN(Reserve Unique Name)サービスを通じて、承認を得る必要があります。
商号は、会社省(MCA)のガイドラインに適合する必要があり、既に登録済の商号と同じ名前や類似する名前、既に登録された商標を侵害するような名前を会社名とすることはできません。最大2つの会社名まで申請することができます。どちらの商号も承認されない場合、異なる名前で再申請を行う必要があります。
申請の際に取締役識別番号が必要となり、添付書類は公証等が付与されたものである必要があります。
申請はオンラインで行うことができ、申請内容に不備がなければ、2~3日で手続が完了します。承認の有効期間は20日間で、その間に会社設立申請を行う必要があります。
【Q10】設立したインド法人の銀行口座を作るにはどうすればよいですか?
設立したインド法人名義の銀行口座を開設するには、一般的には、法人設立時に発行される法人設立証明書と、定款に加え、銀行口座開設を承認する取締役会の決議書と基本税務番号(PAN)が必要になります。
基本税務番号(PAN)はインドの証券決済機構(NSDLまたはUTIITSL)のウェブサイトからオンラインで申請できます。
外資の企業の場合、上記の資料以外にも多くの資料の提出を求められるなど、その手続は容易ではありません。銀行によっては、取締役の物理的な出席を求められることがあり、インド非居住の取締役にとってはハードルとなりえます。
外資系企業向けのサービスが充実している銀行を選び、インドの銀行規制に精通した現地パートナーや専門家のサポートを得ることが推奨されます。
インドの会社法について
【Q1】インドの会社法について教えてください。
インドの会社法は、インドに進出する外国企業にとって、非常に重要な法律です。会社法は連邦法で、全ての州の会社全てに適用されます。
改正を重ね、国際水準のコーポレート・ガバナンス、透明性、投資家保護が図られ、外国企業のインド進出を促進し、ビジネス環境の改善が進められています。
会社法には4種類の下位規則があります。これらの下位規則は頻繁に制定・改正がされるため、常に最新の情報を得る必要があります。会社法および関連法規の最新情報は、インド企業省(MCA)の公式ウェブサイト(www.mca.gov.in)で確認できます。
【Q2】インドの会社法にはどのような特色がありますか?
インドの会社法の特色には次のようなものがあります。
- 公開会社は監査法人を定期的に変更することが義務付けられている。
- 上場企業は取締役のうち少なくとも3分の1を当該企業から独立した取締役とする必要がある。
- 電子文書の保管および電子署名による電子ガバナンスが推進されている。
また、インドでは2013年の会社法改正でコーポレート・ガバナンスに関する規制が強化されました。主な改正内容は次の通りです。
- 情報開示および透明性に関する規定が強化された。
- 特定の条件を満たす企業に女性取締役の登用が義務付けられた。
- 一定規模以上の企業に対するCSR活動費の支出が義務付けられた。
コンプライアンスと規制の枠組み
【Q1】外国企業が必ず毎年行わなければならない手続等について教えてください。
インドで事業を展開する外国企業は、2013年改正会社法に基づき、必ず毎年行わなければならないとされている手続等があります。主な手続等は次の通りです。
-
財務諸表および事業報告書の提出
会社登録局(ROC)に提出する必要があります。
-
取締役会と株主総会の開催
少なくとも四半期に1回の取締役会を開催し、会計年度の末日から6カ月以内に定時株主総会を実施する必要があります。
-
会議の議事録、法定台帳、およびその他社内の重要書類の保管
-
未清算の外国資産または負債(外国負債資産(Foreign Liabilities and Assets、FLA))の申告
-
外国企業の関連企業取引に関する詳細な文書や事業報告書の準備
-
従業員の厚生年金および社会保障に関連する様々な登録や申告
なお、一定規模以上の会社の場合、新たに導入されたESG(環境・社会・ガバナンス)報告規則に基づき、持続可能性および環境コンプライアンスに関する詳細な文書を関連省庁に提出する必要があります。
税務申告に関しては、Q7を参照ください。
【Q2】会計年度末の財務諸表および事業報告書の提出について教えてください。
インド国内にあるすべての会社は、毎年会計年度末に、財務諸表および事業報告書を会社登録局(ROC)に提出する必要があります。なお、インドでは、会社法により、会計年度は4月1日から翌年3月31日までと固定されています。
会計年度の末日から決められた期限内に、所定のフォームを利用して事業報告書を提出します。このフォームには、主要な事業活動の詳細、取締役および役員の情報、財務情報等について記載する必要があります。なお、取締役のうち最低一人は、前年度にインドに少なくとも182日間居住している必要があります。
【Q3】社内の重要書類の保管について教えてください。
すべての会社は、会議の議事録、法定台帳(日本でいう株主名簿、役員名簿、株式譲渡帳簿など)、およびその他の社内の重要書類(定款、会計帳簿、財務記録、取締役会議事録、株主総会議事録など)を保管する義務があります。
外国企業の場合、これに加え、インド国内での事業運営に関する記録を保管する義務が課されており、これらの記録はインド国内に所在する事務所で保管することとされています。
これらの記録は、法律に定められた方法で保管する必要がありますが、書面で保管する方法だけでなく、電子的に保管することも認められています。
【Q4】未清算の外国資産または負債の報告について教えてください。
外国企業は、会計年度末に、未清算の外国資産または負債(外国負債資産(Foreign Liabilities and Assets、FLA))がある場合、毎年7月15日までにインド準備銀行(Reserve Bank of India, RBI)に申告する必要があります。
これは、インドに登録された企業の外国からの直接投資(FDI)や、インドからの海外投資(ODI)に関連する負債および資産の情報を報告するための制度で、インド政府が外国投資のインド経済への影響等を評価・分析するために行っています。
【Q5】外国企業の関連企業取引に関する資料の保管について教えてください。
外国企業は、国際取引に関する移転価格規則によって、取引に関する詳細な文書や事業報告書を準備することが求められます。
関連企業間では様々な思惑から操作された価格で取引がされるおそれがあるところ、この規則は、関連企業間の取引が市場原理に基づいた公正な価格(アームズレングス価格)で行われることを確保し、税収の損失を防止することを目的としています。
外国企業は関連企業取引が公正に行われていることを裏付ける資料を準備しておく必要があります。
【Q6】従業員に関する手続の概要について教えてください。
従業員の厚生年金および社会保障に関連する様々な登録や申告が必要です。
これらの申告は、法改正により簡素化されており、主に電子的なプラットフォームを通じて行われています。従業員の個人情報をオンラインで取り扱うため、デジタルデータの保護やシステムセキュリティ確保のための法律や規制、内部ポリシーの遵守(デジタル・コンプライアンス)が義務化されています。
【Q7】会社の税務申告の概要について教えてください。
インドで会社に課される税金は大きく分けて、法人税と物品サービス税(GST)の2つがあります。これらの税金を申告期限内に納める必要があります。なお、源泉徴収制度もあります。外国企業に適用される法人税率は一般的に約35%とされており、インド国内企業に比して高い税率が課されています。
またインド政府が管理するオンラインプラットフォームにアカウントを作成する必要があります。アカウントの作成には、PAN(Permanent Account Number, 永久口座番号)が必要になります。申告は年に一度行う必要があり、その期限は、監査対象か否か、国際取引があるか否かによって異なります。
物品サービス税(GST)とは、特定の商品やサービスの販売に対して課される税金です。最終的には消費者に課税しますので、日本の消費税と似た部分があります。まず、インド政府が管理するオンラインプラットフォームに登録して、GST登録番号(GSTIN)を取得する必要があります。州をまたがって事業を行う場合は、州ごとにGST登録が必要です。一定以上の売上がある事業者に納税義務が発生します。毎月または四半期毎に申告し納税する必要があります。
なお、2024年現在、売上高が5000万インドルピー(約8.850万円)を超える企業には、電子請求書の導入が義務付けられており、取引の透明性の向上と不正の防止に取り組んでいます。
【Q8】日本企業のインド進出についてインド政府による優遇措置はありますか?
あります。
インドと日本の包括的経済連携協定(CEPA)は、製造業、サービス業、技術移転分野で日本企業に優遇措置を提供しています。CEPAは手続を簡素化し、知的財産保護を強化することで、両国間の投資基盤を強固なものにしています。
日本企業の進出を促進する目的で、インド政府は産業貿易促進局(DPIIT)内に「Japan Plus」窓口を設置しました。この専門窓口は、外国直接投資(FDI)規制関連の承認手続の一元化、投資手続の支援、運用上の問題の解決、および日本企業に影響を与える政策変更の定期的な情報提供をワンストップで行っています。この専門窓口を通じて、FDI規制に関連する情報と支援をリアルタイムで受けることができます。
この他、日本企業向けの経済特区(SEZ)を設けたり、一定の地域に一定の産業分野(自動車など)に関連する日本企業を集積したりするなど、日本企業が円滑に事業を展開できるよう環境が整備されています。
【Q9】外国投資に関する取引の報告の方法について教えてください。
株式の割当や移転、外国直接投資の受け入れを含むすべての外国投資取引は、外国投資報告管理システム(FIRMS: Foreign Investment Reporting and Management System)を通じて報告する必要があります。
外国投資報告管理システム(FIRMS)は、インド準備銀行(RBI)が提供するオンラインプラットフォームで、外国企業に対し、特に価格ガイドラインへの適合性と報告期限の遵守を求めています。外国投資に関する報告と管理を効率化することを目的とし、外国直接投資(FDI)や外国ポートフォリオ投資(FPI)など、様々な形態の外国投資に対応しています。
【Q10-1】日本の投資家向けの資金調達優遇策について教えてください。
(インド政府による優遇策について)
インドと日本は日印財務協議を積み重ね、日本からのインドへの投資を支援する目的で、持続可能かつ環境に優しい金融を理念に、いくつかの資金調達支援策を準備しています。特にインフラ開発、製造業および環境事業については、国際協力機構(JICA)と国際協力銀行(JBIC)が、融資条件を緩和し、なおかつ長期の返済期間を認めるなど特別な融資条件を提供しています。運転資金の調達目的で利用することができ、長期の分割返済が認められることが多く、特定の事業収益と資産を担保にした融資(プロジェクト・ファイナンス)も認められています。
また、インド政府の主導により、The Credit Guarantee Fund Scheme (CGFS)という中小企業向けの資金調達のための信用保証制度が整備されており、一定の業種に該当する中小企業は一定の限度額まで無担保で銀行から融資を受けることができます。この制度は、一部の業種を除き多くの業種が対象となっています。環境保全技術やDX事業も対象業種となっており、外資企業もこの制度を利用することができます。
なお、各州政府も特定の事業分野の振興に取り組んでおり、特定の産業分野や産業地域への投資に対して、利子補給制度や設備投資等の補助金制度を拡充しています。
【Q10-2】日本の投資家向けの資金調達優遇策について教えてください。
(インド現地の銀行による優遇策について)
インド現地の複数の銀行において、インドに投資する日本企業を対象に優遇条件を設け、審査手順を簡素化するなど特別な融資条件を用意しています。運転資金の調達目的で利用することができ、長期の分割返済が認められています。また、特定の事業収益と資産を担保にした融資(プロジェクト・ファイナンス)も認められています。
【Q10-3】日本の投資家向けの資金調達優遇策について教えてください。
(日印ファンドの利用について)
従来型の銀行からの融資による資金調達に加え、日印ファンドの設立により、特にテクノロジーとイノベーション分野において、日本企業のインドでの起業やインド現地企業との共同事業などといった資金調達に利用できます。運転資金の調達目的で利用することができ、長期の分割返済が認められています。また、特定の事業収益と資産を担保にした融資(プロジェクト・ファイナンス)も認められています。
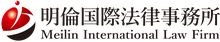
<福岡>
〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル7階
話番号:092-736-1550
<東京>
〒102-0073
東京都千代田区九段北1丁目11番4号 井門九段下ビル8階
電話番号:03-6256-9761
Copyright © 2024 Meilin International Law Firm. All Rights Reserved.
